「探偵業法違反にあたる行為とは何か知りたい」
「そもそも探偵に依頼すること自体が違法ではないのか?」
「探偵に依頼することで問題が起こったら怖い」
本記事はこのような悩みを持つ人の問題を解決します。
探偵業法とは探偵業の適切な運営を図り、悪質な捜査や営業を行う業者がいる状況から国民の利益を守るために制定されました。
違反をすると罰則が課されます。
この記事では探偵業法に違反した際の罰則や事例、違反している業者の見極め方法を解説し、探偵業法違反の被害に遭った際の対処法など相談窓口を含めてご紹介いたします。
この記事はPRを含みます
本記事にはアフィリエイトプログラムを利用しての商品のご紹介が含まれます。本記事を経由しサービスのお申し込みや商品のご購入をした場合、サービスや商品の提供元の企業様より報酬を受け取る場合がございます。
探偵業法違反とは?

探偵業法違反とは探偵が遵守すべき法律に違反し、規則を破った行為のすべてを指します。
罰金や懲役などの罰則も設けられているため、探偵業を運営する際は法律に従って適切な業務遂行を行うことが重要です。
また依頼する側も探偵業法に違反していない探偵事務所を選ぶことで無用のトラブルから身を守ることができるでしょう。
ここでは探偵業法について分かりやすく解説し、探偵業法違反の事例についてご紹介いたします。
探偵業法とは?
探偵業法とは正式名称を「探偵業の業務の適正化に関する法律」といいます。
- 探偵業の適正な運営
- 国民の権利や利益の保護
以上のことを目的として平成18年(2006年)に交付されました。
参考:探偵業の業務の適正化に関する法律|e-Gov法令検索
探偵業法が制定された社会的な背景としては以下のようなものが挙げられます。
- 離婚問題や企業の不正行為など探偵の需要が高まり、探偵業者が急増、サービスも多様化
- 探偵業者の急増に伴い、違法な調査手法、プライバシーの侵害や高額請求など、トラブルが増加し、社会問題となった
- 悪質な業者による不正から国民の権利や利益を守り、探偵業の健全化を目的として法規制の必要性が認められた
探偵業法とは、経済成長や社会の変化にともない探偵の需要が急増し、探偵にまつわるトラブルが問題になった背景から、探偵業の適正な運営と国民の権利や利益を守ることを目的として制定された法律です。
探偵業法違反の事例
ここでは探偵業法違反の事例を法律とともにご紹介します。
これらの違反は探偵業法だけではなく、その他の法律違反にも抵触する可能性があるため注意が必要です。
欠格事由のあるものによる営業
探偵業法違反の事例の1つ目は、欠格事由のあるものによる営業です。
欠格事由とは探偵業を営むものとしてふさわしくない条件を指します。
探偵業法では以下のような項目を探偵の欠格事由として挙げています。
一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
六営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
引用:探偵業の業務の適正化に関する法律第三条(欠格事由)|e-Gov法令検索
上記のように破産手続きを受けて復権していない人や過去5年以内に禁錮以上の刑に処せられた人、暴力団関係者など、法律で定められた欠格事由がある人は探偵業を営んではいけないことが定められています。
無届け営業
探偵業法違反の事例の2つ目は、無届け営業です。
探偵業を営むには各都道府県の警察または警視庁を通して、必要な書類とともに公安委員会へ届け出ることが義務付けられています。
参考:探偵業の業務の適正化に関する法律第四条(探偵業の届出)|e-Gov法令検索
届け出は営業所ごとに実施されなければいけないことや、廃業の際も速やかに届け出る必要があることが定められています。
またこの届け出が受理されると公安委員会から受理番号が交付されるため、この番号を記載した標識を営業所の見やすい場所に掲示したりホームページに記載したりする必要があります。
これらの手続きを行わずに探偵業を営んでいる事務所は探偵業法に違反しており、適切な調査が行われない危険性やトラブルにつながる可能性が高いかもしれません。
名義貸しによる違反
探偵業法違反の事例の3つ目は、名義貸しによる違反です。
1つ前の項目で解説したとおり、探偵業を営むには公安委員会に届け出を出すことが義務付けられていますが、探偵業法では届け出て許可を受けた人が業務を行うことも明確に規定されています。
参考:探偵業の業務の適正化に関する法律第五条(名義貸しの禁止)|e-Gov法令検索
届け出をしていない人に届け出をしていない人が名義を貸すことは、探偵業法に違反している行為です。
不法侵入や盗聴、盗撮、尾行、張り込みなどの過度な行為
探偵業法違反の事例の4つ目は、不法侵入や盗聴、盗撮、尾行、張り込みなどの過度な行為です。
探偵業法では人の生活の平穏を害するなど、個人の利益利害を侵害する行為を明確に禁止しています。
参考:探偵業の業務の適正化に関する法律第六条(探偵業務の実施の原則)|e-Gov法令検索
具体的には、許可されていない敷地への立ち入りや盗聴、盗撮などが該当します。
これらの行為は探偵業法以外の法律にも違反する行為です。
ただし、探偵業の届け出をした探偵が依頼者の許可を得て行う調査は合法とされています。
探偵の尾行が違法にならない理由については以下の記事でも詳しく解説しています。

調査費用や方法、その他の重要な項目についての説明義務違反
探偵業法違反の事例の5つ目は、調査費用や方法、その他の重要な項目についての説明義務違反です。
探偵業法では契約の際に依頼者に対し、調査の方法や調査にかかる適切な費用などの契約内容について書面を交付した上で説明しなければいけないことが義務付けられています。
参考:探偵業の業務の適正化に関する法律第八条(重要事項の説明等)|e-Gov法令検索
依頼しても契約書が交付されない探偵は探偵業法に違反している可能性が高いため、気をつけましょう。
探偵と契約を交わす際に注意したいポイントについては以下の記事で解説しています。

犯罪の助長や差別につながる調査
探偵業法違反の事例の6つ目は、犯罪の助長や差別につながる調査です。
探偵は調査の結果がストーカーなどの犯罪行為の助長につながったり、違法な差別などにつながったりすると知りながら調査を行ってはいけません。
参考:探偵業の業務の適正化に関する法律第九条(探偵業務の実施に関する規制)|e-Gov法令検索
これを違反すると探偵事務所は行政処分を受け、公安委員会のホームページで事務所の名前が公表されることになります。
ストーカーからの依頼や人探しが探偵業法に違反していることについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

個人情報の守秘義務違反や不正利用
探偵業法違反の事例の7つ目は、個人情報の守秘義務違反や不正利用です。
探偵は調査の中で得た個人情報を、本人の同意なしに第三者に開示したり不正利用したりしてはいけないことが探偵業法の中で明確に定められています。
参考:探偵業の業務の適正化に関する法律第十条(秘密の保持等)|e-Gov法令検索
ほかにも情報が漏れないための措置を取ることや従業員に対する教育なども義務付けられていることから、探偵の守秘義務は法律の中でかなり厳格に規定されているといってよいでしょう。
探偵の守秘義務については以下の記事でも詳しく解説しています。
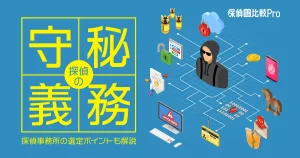
探偵業法違反の罰則

探偵業法違反による処分や罰則についても、法律の中で明確に規定されています。
探偵が探偵業法やその他の法律に違反し、適切に運営されていないと公安委員会が判断した場合、探偵に対し必要な措置を取ることや営業停止または廃業などを命じることができます。
参考:探偵業の業務の適正化に関する法律第十四条第十五条|e-Gov法令検索
行政処分を受けた探偵事務所は、各都道府県の警察署や警視庁のホームページで会社の名前が3年間一般公開されるため、確認するとよいでしょう。
さらにこの指示を無視して営業を続けた場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
ほかにも探偵業法違反に問われた探偵は、違反の内容によって懲役や罰金が課せられることが法律の中でも定められています。
参考:探偵業の業務の適正化に関する法律第十七条から第二十一条(罰則)|e-Gov法令検索
探偵業法違反している探偵を確認する方法

ここまで探偵業法違反の内容や罰則について解説してきましたが、依頼しようとしている探偵が違法業者か気になる人がいるかもしれません。
ここでは探偵業法違反している探偵事務所を確認する方法をご紹介いたします。
探偵業法に違反している探偵事務所を確認する方法は以下のとおりです。
- 公安委員会への届け出があるか確認する
- 直接尋ねる
- 管轄の警察署または警視庁に確認する
探偵業を営むには公安委員会に届け出をする必要があります。
届け出を行ったかどうかについては、届け出をした際の受理番号を記載した標識を営業所の見やすい場所に掲示したり、ホームページに掲載したりしなければいけません。
もし見つけられない場合は直接尋ねてみるとよいでしょう。
これらの番号がない業者は探偵業法違反をしている可能性が非常に高く、依頼は避けることをおすすめします。
また過去に違反歴があるかどうかについては、管轄の警察署や警視庁に確認することで分かります。
特に行政処分を受けた探偵事務所は3年間、名前をホームページに掲載されるため、確認するとよいでしょう。
探偵業法違反の被害に遭った場合の対処法【相談窓口もご紹介】

探偵に依頼していなくても、探偵業法違反の被害を受ける可能性は否定できません。
届け出をしていない探偵から調査された、違法な手段で調査されたなどの場合です。
探偵業法違反の被害にあった場合、以下の4つの機関へご相談されることをおすすめします。
- 国民生活センター(消費生活センター)
- 探偵が加盟している協会や団体など
- 弁護士
- 警察
1つずつ解説いたします。
国民生活センター(消費生活センター)
探偵業法違反の被害に遭ったときに相談できる窓口の1つ目は、国民生活センター(消費生活センター)です。
費用に関するトラブルの相談なら、国民生活センターや消費生活センターが1番身近な相談窓口として挙げられます。
各都道府県にはそれぞれ消費生活センターが設置されているため、調べてみるとよいでしょう。
消費生活センターが分からない人は、ダイヤル188番をかけると「消費者ホットライン」につながり、お近くの消費生活センターを教えてもらえます。
参考:全国の消費生活センター等|国民生活センター
探偵が加盟している協会や団体など
探偵業法違反の被害に遭ったときに相談できる窓口の2つ目は、探偵が加盟している協会や団体などです。
探偵協会や団体の中には、所属している探偵事務所の苦情やトラブルの相談を受け付け、探偵と依頼者の間に入り中立な立場から、解決に向けて働きかけを行います。
ただし、依頼した探偵事務所が協会などに加盟していない場合、この方法は使えません。
探偵事務所にとって協会や団体への加盟は必須ではありませんが、万が一の場合を想定して、依頼の際は探偵事務所が加盟している協会や団体を確認しておくことをおすすめします。
弁護士
探偵業法違反の被害に遭ったときに相談できる窓口の3つ目は、弁護士です。
消費生活センターや探偵が所属している協会または団体に相談しても問題が解決しなかった場合は、法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
金銭的、またはプライバシーの侵害など民事上のトラブルがすでに発生している場合など、弁護士が間に入ることで早期に解決する可能性があります。
依頼した探偵が探偵業法違反に抵触しているようなら、弁護士を通して損害賠償を請求することも可能です。
探偵業法違反の被害に遭ったら、探偵業法に詳しい弁護士の力を借りることで被害の拡大を防げるでしょう。
警察
探偵業法違反の被害に遭ったときに相談できる窓口の4つ目は、警察です。
すでにお金を支払った後だったり、探偵から違法な調査を受けたりと実害が出ているなら、警察が動いてくれる可能性があります。
「#9110」に電話をかければ、各地域管轄の相談窓口につながります。
トラブルの内容に応じて対処してもらえるため、利用をおすすめします。
参考:警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ | 政府広報オンライン
探偵業法違反に関するよくある質問

ここでは探偵業法違反に関するよくある質問とその回答をご紹介いたします。
探偵業を営むのに資格は必要ですか?
探偵業を営むのに資格は必要ありません。
いくつかの探偵協会などでは独自の認定資格や検定などを行っていますが、これらの資格は必須ではありません。
ただし、探偵として開業するには、いくつかの条件と届け出が必要です。
暴力団関係者ではないなどの欠格事由のない人が、警察を通して公安委員会に探偵業開始届出書とその他の必要書類を提出し、手数料を支払う必要があります。
参考:探偵業の業務の適正化に関する法律第四条(探偵業の届出)|e-Gov法令検索”
探偵をつけられたのですが、警察に届け出たり訴えたりすることは可能でしょうか?
探偵をつけられたと感じたとき、警察に届け出たり訴えたりすることは可能ですが、ストーカーなどの身の危険を感じたり明らかなプライバシーの侵害を受けたりしたときでなければ、受理されないと考えた方がよいでしょう。
探偵は依頼を受けてから探偵業法に基づいた調査を行っています。
ただし、届け出のない探偵による調査や違法な手法による調査は、法律で明確に禁じられているため、相談をおすすめします。
下記の記事では探偵の調査がプライバシーの侵害になるケースを詳しく解説しているため参考になるかもしれません。

探偵ができることを教えてください。
探偵に依頼できる主な内容は以下のとおりです。
- 浮気調査
- 素行調査
- 人探し調査・所在調査
- 身辺調査・結婚調査
- ストーカー対策
- 盗聴・盗撮発見調査
一方、調査をすることで差別や犯罪の助長になる案件は、法律で禁止されています。
探偵の依頼できる内容については以下の記事でも詳しく解説しています。

探偵業法に違反していない安心できる探偵を探したい人には「安心探偵.com」がおすすめ!

参照:安心探偵.COM
探偵業法違反に抵触していない安心できる優良な探偵を探している人には「安心探偵.com」のご利用をおすすめします。
安心探偵.comでは相談料無料で厳選した探偵事務所をご紹介いたします。
優良な探偵を探したくても、レストランや病院のように周りに気軽に尋ねられる問題ではないため、どこに相談すればよいか分からない人が多くいるかもしれません。
実際、国民生活センターには違法に営業しているとは知らずに悪質な探偵に依頼してしまい、トラブルの被害に遭った人からの相談が寄せられています。
安心探偵.comは自社の厳しい審査基準をクリアした優良な探偵事務所の中から、最適の事務所を選んでご紹介いたします。
もちろんご紹介する探偵の中に行政処分を受けた事務所はありません。
ご相談は年中無休365日朝7時からよる23時まで専門スタッフが受け付けます。
匿名での相談も可能です。
相談者のお悩みや要望を丁寧にヒアリングした上で適切な探偵事務所をご紹介し、万が一のトラブルの際のフォローやサポート体制も万全です。
弁護士事務所と提携しているため、法的な手続きなどもお手伝いできます。
信頼できる優良な探偵をお探しの人は、最大20%調査費用の割引が受けられる安心探偵.comをぜひご利用ください。

以下の記事では安心探偵.com(株式会社あどまる)の口コミを詳しく解説しています。
の口コミと評判・信頼性を解説-300x158.webp)
まとめ
ここまで探偵業法違反について詳しく解説してきました。
経済の成長や社会の変化にともない、探偵業への需要が高まったものの、探偵にまつわるトラブルの増加が社会問題になった背景の中で探偵業法が成立しました。
探偵業法では探偵が遵守すべき項目を明確に提示しています。
探偵業法に違反すれば、営業停止や廃業の指示を受けるだけではなく、懲役や罰金の刑罰が課されます。
多くの探偵は法律に従って調査を行っていますが、中には違法に調査をしている業者も存在するため、私たちも優良な探偵を見極める力が必要です。
困ったことが起こったら1人では悩まずに、消費生活センターなど適切な機関に相談しながら解決することをおすすめします。
本記事が優良な探偵事務所探しの参考になれば幸いです。









